
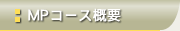
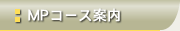
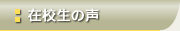
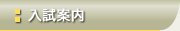
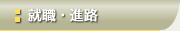
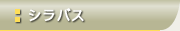
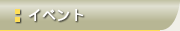


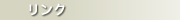
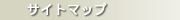
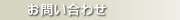
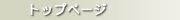
|
| タイプ1:専門深化拡大型履修プログラム | | (1) |
数学から観た量子論
協力学科:数学科・物理学科・化学科
ミクロな世界もしくはナノの世界を説明する量子物理は、現代社会の科学技術を支える物理学の一つである。しかしながら、この量子論は、マクロな世界に住む我々の常識的感覚は通用しない。数学を使って、この量子論を正しく把握する。 |
| (2) |
放射線の基礎から病気診断への応用まで(放射線基礎物理学)
協力学科:物理学科・生物学科
近年、陽子線・X線・ガンマ線は医療用診断、がん治療、構造解析で日常的に使われるようになってきた。加速器ビーム物理、光物性物理、生物物理等の物理学的基礎に重点を置き、その応用開拓を考える.岡山大学の多くの研究者が兵庫県にある世界有数の放射光施設SPring-8を利用し、関連した研究を行っている。その施設へ見学にいったり、生物物性分野等への応用を視野に入れながら基礎科学を学ぶ。 |
| (3) |
先端ナノマテリアル材料の基礎科学
協力学科:化学科・物理学科・数学科
先端ナノマテリアル材料の開発研究は資源の乏しい日本にとって極めて重要な課題であり、研究の基礎に関する幅広い知識をもった者が求められている。本履修プログラムで学ぶことにより、マテリアル材料の設計・合成から評価、ならびに多彩なマテリアル群に対する理解、さらに基礎科学に基づいた総合的な視点に基づく開発研究能力を身につける。 |
| (4) |
金属元素と生命の関わり(生物無機化学)
協力学科:化学科・生物学科
生物無機化学は、化学と生物学の接点に位置する先端分野である。呼吸、代謝、光合成、神経伝達など多くの重要な生体反応の過程において金属イオンの重要性が認識されている。生体反応においてどの金属イオンが使われているのか、なぜ自然はその金属を選んだのか、またどのようにして細胞内にその金属が取り込まれ、その濃度が制御されているのか、特有の機能はどのようにして発現されるか、などを学ぶ。実験室における新物質の効率的な合成への応用研究にもつなげることができる。 |
| (5) |
電波天文学:電波を使って宇宙を見る
協力学科: 化学科・地球科学科・物理学科
星と星との間の宇宙空間は全く何もない空間ではなく、様々な物質が希薄ながら存在している。電波天文学は、光で見える星や銀河とは違う、その母体となる星間物質と呼ばれる分子や固体微粒子の様子をとらえる。星間物質の構造と反応の研究を通じて宇宙における物質の存在形態、変遷を理解し、地球上の物質や生命体の起源を明らかにする夢のある研究領域である。 |
| (6) |
タンパク質や核酸の化学構造と生物機能(構造生物学)
協力学科:生物学科・化学科・物理学科
生体高分子は核酸、タンパク質、糖類、脂質の4種が主たるものである。多種多様な生命活動にかかわっているタンパク質の構造と機能を理解することは現代生物学の大きな目標であり、その成果はバイオテクノロジーや医療などさまざまな分野で応用されている。生体高分子の構造と機能の研究にはさまざまな方法が用いられる。MPコースでは特に生体高分子の構造を研究する物理的・化学的手法の全体像を捉え、将来に必要な研究開発能力を学ぶ。 |
| (7) |
昆虫の発生や成長の調節をしているホルモンの化学と体内での作用機構
協力学科:生物学科・化学科
昆虫の発生過程で重要な役割を果たし、その成長や状態の維持にも働いているホルモンを化学的分析法で検出し、発生や環境変化に応じた変動をとらえることにより、ホルモンの分泌や作用の制御メカニズムを明らかにする。また、ホルモン受容体に作用する新しい化学物質を合成する事により、昆虫に特異的に作用する安全な農薬開発に結びつける。 |
| (8) |
地球のはじまりと生命の歴史
協力学科:地球科学科・生物学科・化学科・農学部
地球上に生命が誕生し,進化したかは,人間にとって究極的な問である。分子生物学の進歩,地球の表層環境歴史の解明,高温高圧など極限環境に生きる微生物の研究やそうした場の化学環境の測定などにより,生命の誕生とその初期進化について,新たな考えが唱えられつつある。地球科学と生物学の境界領域であるこの分野を学ぶ。地球の初期生命史にとどまらず,現在の地下生物圏の探査や生物資源としての利用にも目を向ける。 |
▲トップへ戻る
<<BACK
|